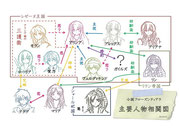Ⅻ 道
「盗賊に襲われた?」
「おかしいな。タプ港からのこの一本道は、金持ち商人なんかが全然通んないから、盗賊はあまり出ないと聞いたんだが」
近くに流れる小川を見つけた三人は、川辺の岩に腰掛け、アリシアの話を聞く。
顎髭を撫でながら首を傾げるアモス。アリシアのスカートに付いた血痕を落としながら、ディージェイも眉をひそめる。
「まあ、立派な馬車に乗ってたから、つけられてたのかもね」
ぽつり、とそう呟いたディージェイに、アリシアは心外だと言い返す。
「そんな! カルスまでの馬車はすごく小さいのを使ったし、ここまでは歩いてきたの……来たんですよ?」
「おいおいディージェイ、いくらなんでもこんな場所まで、わざわざ立派な馬車で来るか?」
いきなり根拠の無いような事を言い出した彼を諌めるように、アリシアの肩を持つアモスだったが、それでもディージェイは静かに問うた。
「じゃあさ、どうしてこんな場所に我が国の姫君が、いらっしゃるのかな?」
「全く、けが人にこんな仕事を任せるなんて……」
紫乃とローリアは、モランの応急手当だけを施し、駆けて行ったアリシアを探しに行った。
残されたモランは休み休み、死体の処理を片腕で行う。頭領らしき少女は残ったが、生残った者達数人は皆逃げだした。これから彼らがどうやって生きていくのかはモランに関係のない事だが、これからまた盗賊家業ができる程腕の立つ者はいないだろう。
「ねえ、あんたら、貴族? あんな武器初めて見たよ!」
頬に涙の跡を残し、少女が問う。逃げられないように拘束されているが、彼女はそれでも屈託のない笑顔を見せた。
(しかし……信じられないな。この少女が、あいつらをまとめていた頭、だなんて。……世も末か)
配下の者達を失い、嘆き叫んだ絶望の内に意識を手放した少女を、あの二人は生かした。
本来ならば、王家の人間に手を出した時点で死刑は免れない。即刻命を絶たれてもおかしくはないのだ。例え、それが僅か十四、五歳の少女であったとしても。
「ねえ、あんたも持ってんだろ? あの武器、見せてよ!」
「持っているのはあいつだけだ。俺は持っていない」
目を覚ました途端、この調子でやたらと構ってくる少女は、どういうつもりなのだろう。
「へえーじゃああんたの武器ってその剣だけ? あっそれ何カッコいいじゃん、もっと近くで見せて!」
その言葉に、モランの方眉があがる。
「成る程。俺を殺して逃げるつもりか」
「そんなこと……。ま、ばれちゃあしょうがないけど。だってあんた弱そうじゃん? 間抜けにも落とし穴にはまってさぁ。その肩も、止血下手なんじゃない? 結構辛いでしょ」
眉間の皺が深まる。ローリアが巻いた包帯は、死体を処理しているうちに緩まり、流れ出した血に染まっていた。押し寄せる目眩を彼女に悟られぬよう腰を下ろす。
(くそ……ローリアめ……)
応急処置と言いながら適当にぐるぐると巻いただけの彼女。しかし今更恨んでも遅い。
「ねえ、あんた。女神様が本当にいるって、信じてんの?」
死体を埋めた場所に立つ、聖剣を模した十字の木を顎で指す少女。
レゼーヌ王国において、女神の存在は絶対であった。女神の血を引く王族に力があるのも、その元で民衆が暮らして行けるのも、皆女神の加護を受けている証なのだ。だからこの国に生まれた者は皆、幼い頃から神を崇め、国王を慕うよう教育されている。
つまり、神の存在を否定する者は異端であり、国家反逆の罪を問われる事もあった。
「お前は、どう思うんだ」
ある程度の予想はついたが、ふと、少女の悲しげな表情を見て問う。
「あたしの名前、アリアってんだ。どっかの馬鹿が付けた名前か知んないけど、笑っちゃうよね」
神の名は、上位の神官しか口に出す事を許されない。しかしその名の一部分を取って子供の名前に付けるのはよくある事で、現にアリアという名前はレゼーヌ王国での一般的な女性の名前だった。女神の加護があるように、と両親達は願って付けるのだろう。
「その馬鹿は、戦争で死んだよ。あたし一人置いて、焼け死んだんだ」
幼かったアリアに、両親の記憶は殆どない。覚えているのは、焼け付く炎と言葉に出来ない怒りや悲しみなどの強い感情、そして幼いながらに深く感じた、絶望。
「そんであたしは、盗賊団の親分に拾われた。んで、今のあたしがあるって訳」
いつの間にか身の上話を始めた自分が急に気恥ずかしくなり、アリアは話を切り上げた。しかし、少女の心に詰まった感情は流れ出し、そのまま言葉を紡いでゆく。
「あたしら本当は、死ぬとか生きるとかどうでも良いんだ。欲望のまま人殺して生きて、それもいつかは殺されておしまいになる。だから、誰かが終わらせてくれんのずっと待ってるのかもしれない、って」
数年前、盗賊団の親分が処刑された後に、副団長が言った言葉だった。アリアの傍らでいつも面倒を見ていた隻眼の副団長は、木の十字が立つ土の下で眠っている。
「ねえ、やっぱ、もういいや。処刑なんかよりも先に、あたしもあいつらと同じように眠らしてよ」
溢れ出す涙を拭う術も持たないまま、口の端を上げて笑おうとする。
「あたしいつも助けられてさ、みんなあたしの目ん前で、馬鹿みたいに死んでくの。……もう、一人で生きる時間なんて欲しくない……一秒でも、欲しくなんか無い」
家族も、家も失い、そして居場所まで失った。これが、今まで犯した罪への天罰ならば、この身に今すぐにでもその罰を受け、解放されたかった。
「くっ……」
泣いているのか笑っているのか、自分でもわからないままひたすら死を請うアリアに、先ほどから彼女の向かいに座って沈黙していたモランの体が傾き、その場に倒れる。
「え、あ、あんたどうしたの? ねえ!」
(な、あたし何言ってんの?)
仲間を殺した敵の一人で、先ほどまで殺そうとしていた相手だ。しかし思わず口をついて出てしまった言葉に、動揺する。
「……い、きて」
「え? な、なんだって?」
「生きて、欲しかったんだ、ろう」
流れ出す血液と共に、徐々に朦朧としてゆく意識の中で、重たい口を動かすモラン。
「お前はずっと、愛されて、何かを、想いを、託されて生きてきたんだろう。お前を愛した奴らの……命は、お前の中で生きている、んじゃないか」
「だって……!」
目の前に倒れたモランと、副団長の最期が重なる。
アリアをかばって背に大きく傷を受けながらも、残った力で口だけ動かし、こう言った。
『終わった、やっと』
(違う……!)
涙でぼやけた視界が捉えた口の動きは、こう言ってはいなかっただろうか。
『おまえは、生きろ』
「っ————!」
感情の波が一気に押し寄せ、言葉の代わりにただ、涙がこぼれた。どうしようにも止められず、モランに背を向け泣きじゃくる。
今まで重く背負ってきたものが、アリアの罪だけではなく、彼らの願いと共にあるものならば。生き延びてきた事が、罰ではなく、誰かが命がけで託した、希望だったのならば。
不意に、何かが破れる音がして、両手が自由になる。
「行け」
「え……?」
モランの握った小刀が、アリアを後ろ手で縛る縄を絶っていた。
「お前は、生きるんだろう? ……早く行きなさい」
「ちょっと待って、あ、あんたは大丈夫なの?」
アリアの言葉に、場にそぐわぬ優雅な微笑みを、血の気の悪い顔に浮かべるモラン。
「少し、血液が足りないだけだ、ろう。モンブラン、でも食べていればじきに、良くなる」
「何で……」
「早く行かないと……後でまた、捕まったりしたら、地獄のおし、おきだ————」
それを限りに意識を失ったモランの前で呆然とする。
手は、自由になった。足の縄も、この刀を使えば簡単に切れる。そして一目散に逃げれば、もしかしたら他の奴らが帰ってくる前に逃げ切れるかもしれない。……けれど。
「……これ、本当にへたくそな巻き方」
足の縄を切り、地に伏すモランを見下ろすアリア。
「あ、あたしの方がずっと上手く巻けるってーの!」
足には、自信がある。手近な布を裂き、アリアは作業に取りかかった。
「はあっ、はあっ、っ」
彼の手当は思ったより、時間がかかった。幸い、まだ今の所は奴らに見つかっていないが、恐らく近くにいるだろう。しかしアリアが目指したのは、ここからそう遠くない、盗賊団の幌馬車を停めた場所だった。
(親分の手帳……。あれだけは、もってかなきゃっ)
舗装された道路と粗い砂利道の境界から横に逸れ、茂みの陰に隠された数台の馬車を見つける。そして頑丈な錠が掛かった、ひと際大きな馬車の扉を開き、中に駆け込んだ。
「あった……」
決して大きくない、しかし頑丈で、立派な革張りの使い込まれた手帳を見つけ、アリアはそれを両腕で大事に抱えた。顔を近づけると香る、革にしみ込んだ葉巻の匂いにまた、涙があふれそうになり、それを強く抱く。ろくに読み書きもできないアリアだったが、それだけが唯一、彼女に残された団長の形見だった。
「あたし……これから、どうすればいいかな?」
一人だとは、思わない事にした。ただ、それでもどうしようもなく心細くて、ふと、奪い取った物らが入った大きな箱を開ける。
「っこれ……」
薄汚い木箱に収められた数々の宝物の中で、群を抜いた輝きを誇るティアラがそこに鎮座していた。
商人らしき人物からつい先日奪ったものだ。アリアも副団長も今までに、これほどの価値の物を目にした事はないくらいの大物だった。
(そうだ……あたしらはこれを売ろうとして、カルスに行って……)
道端で金貨を配るような、とんでもない貴族らしき少女を目にし、ここまで追ってきたのだ。
先回りをして落とし穴を掘る所までは、上手くいったと感じていたが、結果はたったの二人相手に殆どの仲間が命を落とした。現に、誰かが戻っているかもしれないと少しの希望を抱いてきたここには、全く人の気配が感じられない。
「これ売ったら、どれくらいになるんだろ」
一瞬、その高潔な姿に触れるのを躊躇うが、アリアはもう輝きから目を逸らす事ができなくなっていた。
「これさえあれば……————」
「お前! こんな所で何をしているっ!」
「っ!」
振り返った瞬間、大きな衝撃が一つ、体を抜ける。
何が起こったかも分からぬまま、彼女が最期に目にしたのは、燃えるように揺れる、紫の大きな双眸だった。
「どういう事だ! どうしてこんな所にフローズンティアラがある!?」
「ウィリアム様……」
少女の亡骸が手にしたティアラ。計画が上手く運んでいれば、ここに有り得るはずの無いものだった。
「盗まれたと……いうことなのか? ならば、私の妹は……」
「殿下とマリア様には、私の兄が付いています。恐らく無事でいらっ————」
「しかしだな!」
「話を聞け!」
「っ!」
ひどく狼狽える主に、侍女らしき少女が一喝する。
「失礼しました。けれど陛下、今ここで我を忘れてどうするのですか?」
「……チッ」
冷静な一言に、少女に背を向けて苦々しそうに舌打ちをするウィリアム。
「ほら、ティアラを今からそんな風に握ってはだめです。“彼女”は貴方の肉を簡単に裂いてしまう」
明らかに主人の気分を害したとは思ったが、少女は怯む様子も無く、拗ねたように黙り込む背中に言葉をかける。
フローズンティアラを握った彼の手からは、それほどの力を入れていないにも関わらず、幾つもの紅い雫が滴り落ちていた。
それに気付いたウィリアムは一息、自嘲したような溜息を吐く。
「……ここでも私は、無力なのか」
自分の血を吸って、まるで生きているかのような輝きを放つティアラを眺め、呟く。
両親を亡くし、祖国を追われ、たった一人の肉親である妹さえも、自らの手で救い出す事は叶わなかった。
(憎いのは、誰だ)
叔父上が憎い。レゼーヌが憎い。シャールが憎い。
(けど私が……俺が憎いのはっ)
背伸びをした口調。強くなろうと足掻く、弱い、無力な己自身。
それ故に、強くなると決めたのだ。どんな手を使ってでも、強く、なるのだと。
「なあ、私は————。間違ってない、よな」
「っ! ……ええ」
戸惑うように発せられたその一言に、少女は僅かに狼狽える。
初めて出会った時から、王たらん気品と気丈な精神を感じさせていた彼が、配下の者である彼女にここまで弱気な態度をとった事があっただろうか。度々こうして見つめる、決して大きくはないその背中は、しかし一時として翳る事が今までにあっただろうか。
まさか、この若き主君は未だ、彼女のことを。
「いや、すまない。今のは忘れろ。で、このティアラは……————っ!?」
振り返った途端、もの凄い勢いと力で抱きしめられるウィリアム。
「ウィリアム、様っ」
少女の突然の行動に、ウィリアムはひどく驚いた様子でその目を見開く。
「な、何だ、お前。ちょ、うっ、くるしぃ」
真っ赤になって引き離そうとするが、彼より頭一つ分も背の低い小柄な少女は、何か執念を宿したかの様に、しがみついて離れない。
「本当に、貴方という人は……」
「……」
少女は呆れたようにそう呟き、抵抗を止めたウィリアムを解放する。
(この気持ちは、何? 心がどうしようもなく痛い。何でだろう、勢い余って思わず絞めてしまった)
予想以上に赤くなっていた彼は、少女と目が合うと気まずそうに視線をそらした。
少女も流石に力を入れすぎたか、と彼の血液循環について少し心配する。
「私は、付いていきます。ウィリアム様、貴方の進む道どこへでも。貴方が望む限り、私は邪魔するものを切り払い、その道を先へと繋ぐ駒となりましょう」
自分自身を駒だと称し、少女はひたとウィリアムを見据える。
「……それが、許されざる道だとしても、か」
「それが、ウィリアム様の選ばれた道ならば」
静かで、ゆっくりとした時間が束の間、流れる。瞼を降ろし、耳を澄ませると聞こえる、息遣い。瞼の裏に思い浮かんだ、向日葵のように明るい笑顔へそっと、別れを告げるウィリアム。そして再び目を開けるとそこには、いつもと変わらず真っすぐな、薄いラヴェンダー色の瞳があった。
(俺の選んだ、道)
決して、正義の道ではない。幾人もの人間を欺き、裏切って進んで来た道だ。
それは、己こそが選んだ、ただ一つの道だから。後戻りはできない。
「我らが進む、不義の道に」
「大いなる神の祝福があらん事を」
掲げた右手を合わせ、二人は神へ祈りを捧げた。
「フローズンティアラが消失したと、言ったか」
「はっ。かの国はそれを極秘に留めておりますが、城内や軍はかなり混乱している様子。この数日、国境の警備がやたらと厳重になったのもその為かと思われます」
凍てつく雪が大地を覆う、北の大国、リラン帝国。残忍とまで言われる手法と確かな治世力で知られる中年の皇帝は、又とない好機ににやりと微笑んだ。
十年前の戦は、各国小競り合いの末に終わったがいずれ、また争いは起こるだろう。
レゼーヌが混乱の渦中にある今、攻め入るには絶好のタイミングであった。
「体裁などどうでも良い。準備が整い次第侵攻するぞ」
「はっ」
必死の思いで手に入れた玉座を満足そうに撫で、ほくそ笑む皇帝。
「私の目の黒いうちに、レゼーヌ城は、必ず落としてみせる」
そうして、雪原に住まう群青の竜(ドラゴン)は、南の赤獅子に牙を剥いた。
ランキング参加中。よろしければクリックを↓